気密改善計画の一環として、ユニットバス周辺には何か問題があるかもしれないと思い、とりあえず潜ってみることにしました。
床下は軽く覗いてみたことがあるだけで、潜入するのは初めてです。
すると、”思ってたんと違う” ことだらけで、衝撃を受けてしまいました。。
浴室断熱はこうあるべき
予備知識ゼロで潜っても何もわからないので、まずはユニットバスまわりの断熱・気密について勉強することにしました。手持ちの本には詳しい説明が見つかりませんでしたが、以下の Web ページが参考になりました。

三井ホームの場合、家のサプリの動画も参考になります。
これらを見て学んだのは、床断熱の住宅であっても、浴室まわりだけは基礎断熱にすることが望ましいということです。それが無理でも、準じて、ユニットバスの床下部分だけでも外気の流れを止めておくことが望ましいようです。
わが家の浴室はおそらく、
・基礎断熱ではないだろうし、
・人通口は塞がれていなそう
・基礎パッキンの隙間も塞がれてないかも
などと考えていましたが、想定が甘すぎました。。
床下の気流がツーツー
防災用に購入していたLEDランタンを床下に置き、まず驚いたのが、浴室まわりに基礎の立ち上がりがないことです。
浴室と洗面のみならず、玄関くらいまでが一つの連続した床下空間になっていて、浴室の床下が区画分けされていません。人通口や基礎パッキン以前の問題です。
当然ながら、ユニットバス直下も外気はツーツーです(冬で 12℃くらい)。
前出の教えて、「断熱さん!」の解説で「論外」と書かれている、「図・悪1」のような感じです。
浴室下部の断熱がテキトー
論外とはいえ、ユニットバスの下部には一応、断熱材があります。無断熱というわけではありません。
しかし、ライトを照らして浴槽の下を一目みると、またしても衝撃を受けてしまいました。
断熱材がめっちゃ薄い!サーモバス仕様にしたのに?
しかもでっかい穴が開いている!!
なんで今まで誰も気づかなかった!?
点検時にも見て見ぬふり?
・・・
穴の奥に見えるのは、浴槽です。つまり、浴槽が外気に直接接していたわけです。
こんな状態で高断熱住宅の浴室は寒くない(キリッ)なんて記事を書いていたのが馬鹿々々しくなります。
また、ユニットバス自体の断熱は、浴槽部も洗い場の部分も、想像以上に貧弱です。下調べ不足でしたが、今になって調べるとメーカーによる差が結構あったので、次の記事で紹介します。
▶ ユニットバスの断熱性能比較(リクシル、TOTO、Panasonicほか)
ユニットバスと住宅内壁の隙間は大きい
次にチェックしたのは、ユニットバスと住宅躯体との接続部分です。これは普通のことのようですが、ユニットバスと土台の間には、結構大きな隙間があります。だいたい 4cm くらいでしょうか。
ここがもし塞がっていなかったら、壁内にも冷たい外気が入り込み、断熱的に問題となることは容易に想像できます。壁単位で気流が止まっているツーバイ工法ならまだしも、在来工法では大きな問題になりかねません(前出・水先案内人さんのページで図説されています)。
わが家の場合、この隙間は、以下のように黒いベタベタするスポンジ状の断熱材(?)が二つ折りになって塞がれていました。
きちんと塞がっているのかは、前出の動画をみると怪しいところです。また、浴室の表面温度を測ったとき、ユニットバス床の側面が周囲より低温だったため、ここが断熱の弱点になっていることは明らかでしょう。
浴槽まわりは内壁が外気と接触
もう一点、気になったのは、浴槽と内壁の接続部分です。
以下の画像は、右手が外壁面で、左側が浴槽、正面奥が室内(脱衣所)の壁です。
これを見ると、外壁面(右)にはべーパーバリア(防湿気密シート)が貼られていますが、内壁(奥)には外気が直接接しています。
外壁面はツーバイシックスでも、内壁はツーバイフォーなので壁は薄くなっています。
薄いだけならよいですが、ここが「外気に接する面」として処理されているのかは疑問です。つまり、この面には断熱材があり、内壁の脱衣所側にはべーパーバリアが貼られている必要があると思うのですが、そうなっているのかはやや心配なところです。5年住んでも特に問題は見つからないので大丈夫と思いたいですが。。
念のため、室内側で壁の表面温度を測定してみると、案の定、周囲より温度が低くなっていました。ただし、よくよく調べてみると、温度が低いのはそこだけではなく、外壁面と 1F 床面の接続ラインはほぼすべて、温度が低くなっていました。防湿気密シートと床面の気密処理が甘い(気密テープで留めていない?)ため、すき間風が入ってきているのでしょう。
前出の動画においても、巾木の隙間からスモッグが上がっていたので、この隙間を埋めればマシになるかもしれません。そのうち以下製品を使用して対処したいと思います。
床下を舐めていた…
ちなみに断熱・気密とは関係ありませんが、床下に潜ることがこんなに大変なことだとは思っていませんでした。
長期優良住宅では床下を点検できるよう十分な高さを確保することが定められているため、「ほふく前進で移動できるだろう」、「虫の死骸があったらイヤだなぁ」くらいに思っていましたが、いざ点検口から体を入れようとすると、体全体を収めるだけでもやっとのことです(身体のかたさには自信があります)。
床下の高さを手で測ってみると、35cm ほど。ちょうど身体の横幅くらいなので、ギリギリ寝返りできるだけです。虫の死骸を気にする余裕もありません。
ほふく前進も難しく、イモムシのように移動するしかありません。動くとお腹が出てしまうので、「つなぎ」を着ればよかったな、と少し後悔しました。
後で調べたら、長期優良の条件は「床下空間の有効高さを330mm以上とすること」だったので、これは一般的な高さのようです。
そんな高さしかないうえに、床下には配管やらボルトやらが通っているため、移動は危険でラクではなく、細かい作業は困難です。
取り急ぎ対処したこと
上記のように状況を確認した結果、これは放置できないと思ったので、以下の処置を行いました。
・浴槽下の断熱材の穴を気密テープでふさぐ
・念のため、ユニットバス下の外周を幅 10cm の気密テープでふさぐ
ユニットバス下の外周部は余裕があれば断熱材を入れたいところですが、大変そうなので諦めました。浴室の寒さに悩まされているならともかく、別にストレスを感じていないので、施工が億劫です。
その後、住宅の気密性能が少しは改善したかと期待して簡易気密測定を行ってみましたが、差圧の変化は見られませんでした。温度もあまり改善しません。
おそらく、ユニットバス自体は防水がしっかりしているので空気が入り込まず、ユニットバスと住宅本体の隙間については元々問題なかったのかもしれません(粘着断熱テープ処理で間に合っていたのか、ツーバイの壁だからかは不明です)。
わが家の場合、気密というより断熱の問題が大きい感じです。
良かったところ
今回の床下チェックはガッカリすることばかりで残念でしたが、良かった点も挙げておきたいと思います。
配管の穴は発泡ウレタン施工済み
床の断熱材では配管用に開けた穴がそのままになっているのではないか、などという心配もありましたが、それは杞憂で、一応発泡ウレタンで塞がれていました。十分ではないかもしれませんが、ないよりはマシでしょう。
結露などの跡はない
どこかで結露やカビが発生しているかも、という心配もありましたが、2月でも目に付く問題はありませんでした。漏水などもないようです。
ヤバいいきものはいない
床下にはクモとかダンゴムシくらいは居そうだし、もしかしたらゴキブリやカマドウマなんかもいるかもしれないと心配でしたが、その点も大丈夫でした。クモの巣や死骸は少しありましたが、気にする余裕もなかったので、息で吹き飛ばして進みました。
蛇足ですが、以下の本が好きです(どれも未体験)。
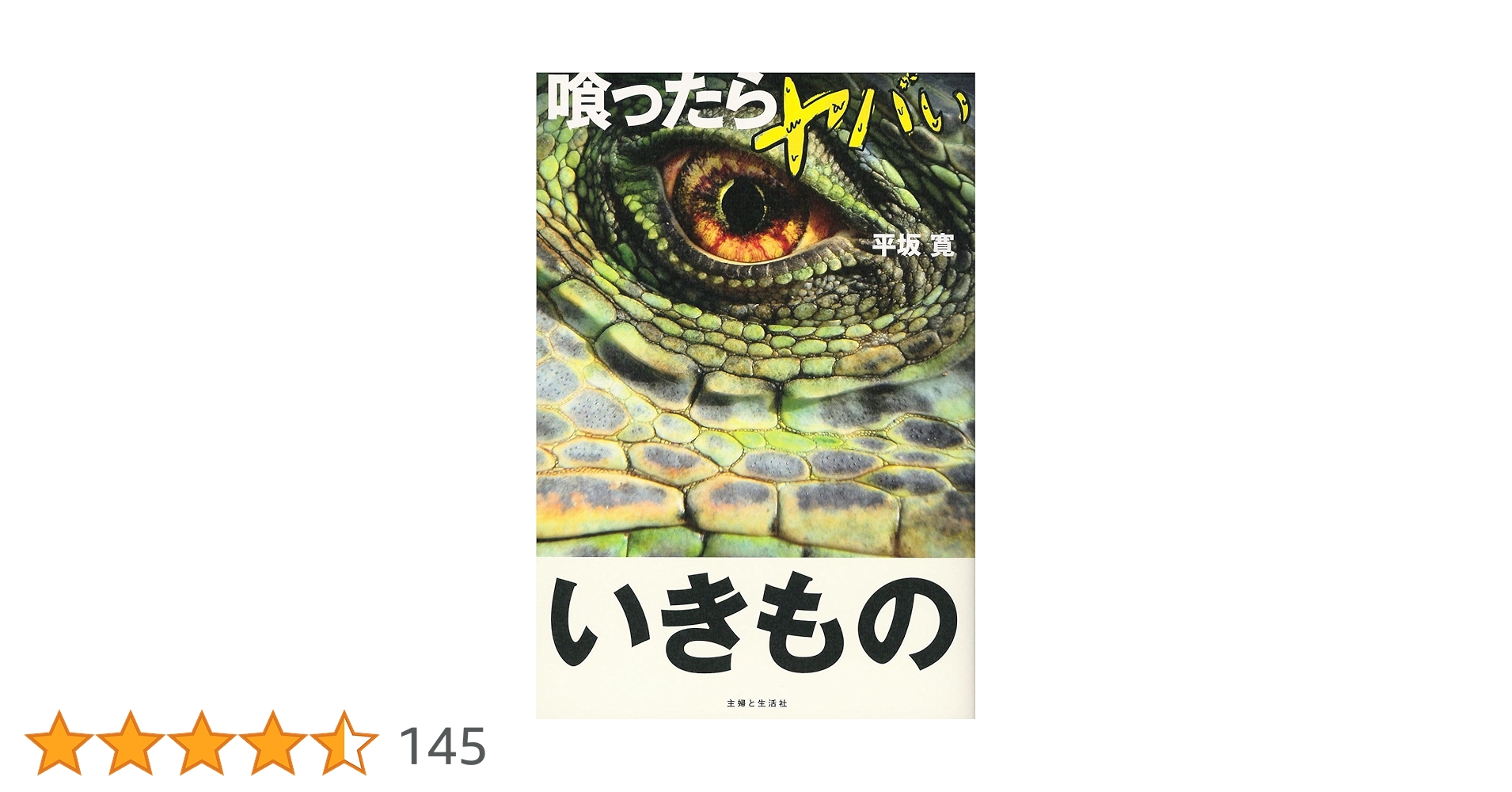







コメント
楽しく拝見させて頂いております。
黒いベタベタするスポンジ状の断熱材は「エプトシーラー」という部材かと思います。(表面は発砲されたスポンジ状ですが、写真で見えているのは裏側の接着面と思われます)
ユニットバスと住宅躯体との接続部分に限らず、気密部材として使用されるようです。(その他、音に関する対策部材としても使われる)
情報ありがとうございます。
少し探してもわからなかったので助かります。
EPDMゴムなら耐久性もありそうですね。