2024年7月末、なんとなく宅建士の試験に申し込んでみました。
別に宅建士の資格が必要というわけではないのですが、将来的に土地建物の取引に関する知識が必要になりそうなので。
宅建士の資格をとるためには、一般に 400 時間以上の学習が必要といわれています。
が、そこまでやる気はありません。多少の基礎知識や経験はあるはずだから、それなりに勉強してみて、合格できたらラッキーくらいの感覚です。
学校や通信講座を受ける気もなく、完全独学です。
ここでは、10月20日の試験に向けて8月頃から開始した勉強の内容と、実際の試験結果について書いておきます。
試験対策としてやったこと
まず昨年の試験を解いてみた
試験で問われるのはどんな内容なのか、現時点の知識でどれだけ得点できるのかが気になったので、まずは過去の試験を1回解いてみることにしました。
結果、50点中15点。
合格点の36点には到底届きません。4択のマーク式の試験なので、サルでも12~13点とれる計算ですが、それよりちょっとマシなだけです。
都市計画法や農地法、税法などは少しは知っているので、もう少し得点できるかと思いましたが、問われる内容が細かく、さっぱり解けません。最後の土地と建築に関する知識問題を除くと、ほとんどが意味不明でした。
これはなかなか手ごわそうです。
なお、このときは採点のみで、正解は確認していません。
テキストをざっと読む
その後、まずは基本テキストをざっと一通り読んでみました。こちらの 2024 年版の書籍です。
テキストが分厚く、約 800 ページあるので、重要そうなところや読んで理解する必要があるところを中心に、細かいところは飛ばして読みました。だいたい 1 時間に 20~30 ページくらいのペースで読み進めたと思うので、30 時間くらいかかったのではないでしょうか。
なんとか読み終え、最後に厳選過去問50問を解いて軽く復習したところ、気づいたら試験本番1週間前になっていました。
計画性がなさすぎです。
もう一回昨年の試験を解く
この時点でもう一度過去問を解いてみたところ、結果は 50 点中 26 点。
あと1週間しかないのに、合格点には10点も足りません。
今年の合格は難しいと思いましたが、得点できなかった分野は「宅建業法」と「法令上の制限」に関する問題が中心です。
これらは、要点さえマスターすれば短期間に得点を伸ばせる分野でもあります。
解法テクニックを学ぶ
ここで、過去問の解説を検索していて見つけたサイト「過去問徹底!宅建試験合格情報」の「宅建」高速解法テクニックを学習してみました(無料)。
既に分かっていた分野は飛ばし、4時間くらい学習したと思います。
これはとてもわかりやすく、大変役に立ちました。
一昨年の過去問を解く
この時点で一昨年(R4年)の過去問に挑戦したところ、結果は 50点中38点。合格点は36点だったので、ようやく合格圏内です。
なお、ここまでの過去問は、すべての選択肢を熟読し、知識が曖昧だったところはしっかり復習しました。
過去問演習
もう合格できるのではないかと油断しつつありましたが、過去問3年分くらいは最低限解くべきでしょう。
R3年の過去問にも挑戦したところ、結果は 50 点中 34 点。合格点ギリギリです。
やっぱり安心はできないと気を引き締め、直前(当日朝)は最新の統計情報をチェックした後、仕上げとして過去問を繰り返し解いていました。
次のサイトの過去問道場はとても有益でした。
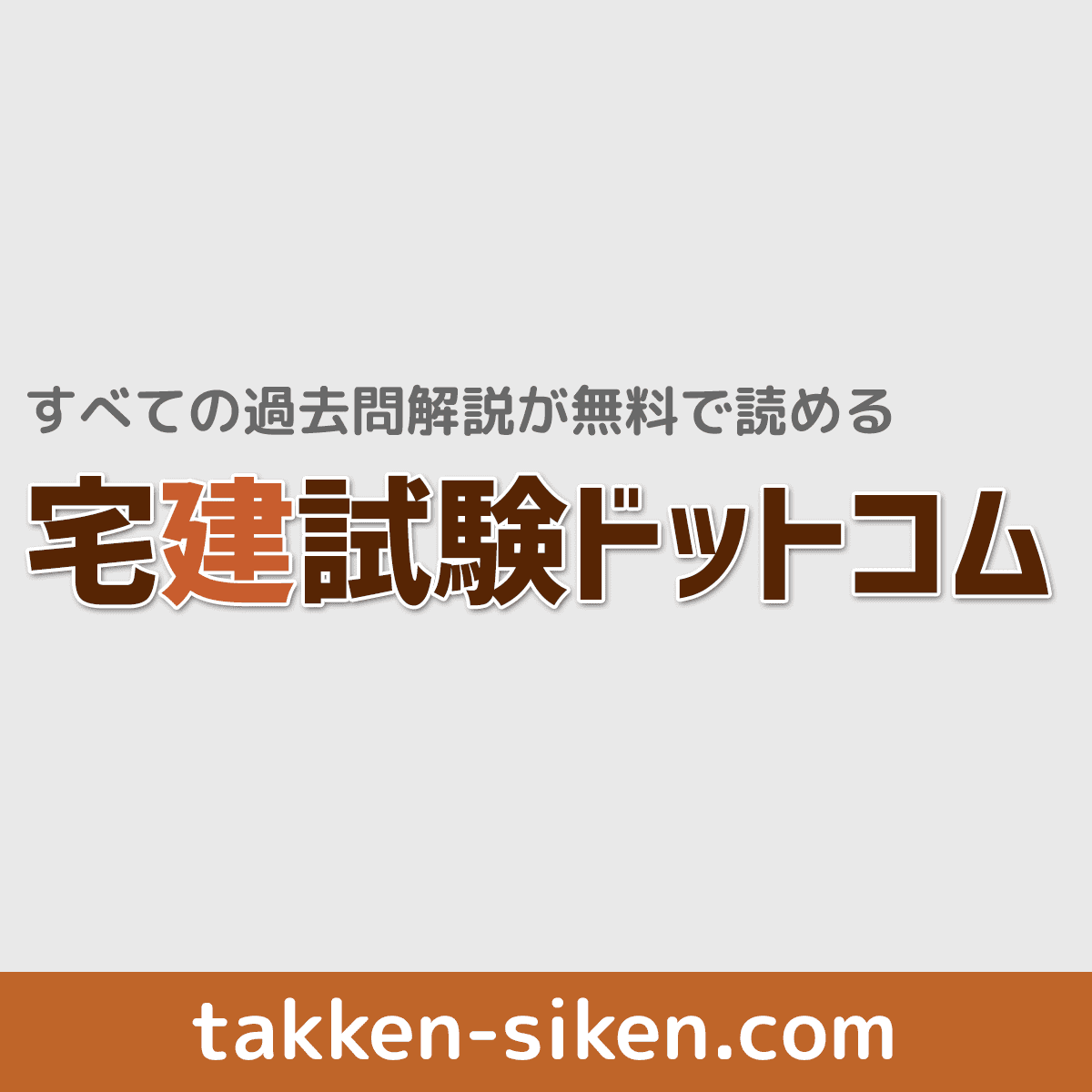
はじめは7割くらいの正答率でしたが、繰り返すと9割近くになっていきました。
よく出題される論点や文章に慣れるのは大事です。
試験結果
そんな感じでR6年10月20日に実際の試験を受けたところ、結果は自己採点で 36 点でした。
TAC の予想合格点の 35±1 点は超えていますが、多くの塾は 37 点と予想しており、たぶん落ちたのではないかという、絶妙なラインです(追記:最終的な合格点は 37 点で、ちゃんと落ちてました)。
いくつかのケアレスミスが悔やまれるところですが、結局は学習不足です。
ちゃんと民法や税法などを学び直し、過去問を10年分くらいはやっておくべきでした。
来年、再挑戦するかどうかは未定です。
宅建士を受ける意味はあるか?
当サイトのテーマである、新築住宅を購入するというのは、宅地建物の取引の一つです。
そのため、宅建で勉強する知識の中には、知っておいたほうが良かったと思うことや、役立つであろう内容もありました(民法など)。
とはいえ、宅建士に合格できるほどのレベルが必要かというとそうではないので、関連しそうな分野をテキストでチェックするだけでも十分でしょう。
むしろ、宅建の勉強では学べない重要なこともたくさんあるので、住宅を1回建てるためだけに宅建をとるのは非効率でしょう。
不動産業や不動産投資とかに興味のある人が受ければよいのではないでしょうか。
宅建士は独学か通学のどちらがよいか?
宅建士の資格を効率的に取りたいという場合や、合格率を上げたい場合、何らかの学校に通うのはお勧めです。
お金をかければ、それだけ損しないように勉強時間を確保するだろうし、勉強法がよくわからない場合はカリキュラムに沿って学習するのが効率的でしょう。
どの学校がよいのかは、合格率の定義が各社異なるのでわかりません。この合格率がクセ者で、分母が受講者数ではなく、模試で上位成績を収めた人だったりします。
そのため実際は、独学で合格することも難しくはありません(資格試験に慣れている人であれば特に)。優れた教材本は多く市販されているし、ネットで学習できるサイトや過去問、動画も多数あります。
最新の法律がよく出題されるので、最新のテキストを購入し、あとは過去問演習を繰り返せば、合格レベルに達することは十分可能だなと思いました。





コメント